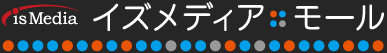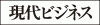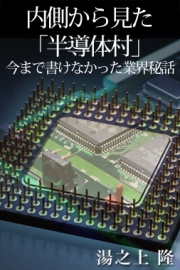
内側から見た「半導体村」 今まで書けなかった業界秘話
湯之上隆
動画コンテンツを含む商品の場合は、「動画コンテンツ動作保証環境」ページをあらかじめご確認のうえお申し込みください。
著者メッセージ
いま世界では、半導体が単なる工業製品ではなく、国家の安全保障と経済力を規定する戦略資源として扱われている。AI、軍事、エネルギー、金融、通信──あらゆる領域の基盤を支えるのが先端半導体であり、各国はその製造能力を国内に確保するために、これまでにない規模の資金と制度を投入している。これは一時的なブームではなく、明確な潮流である。
こうした中、日本は長らく失われていた半導体製造基盤を再構築しようとしている。TSMCの熊本誘致、Rapidusによる2nmロジック量産への挑戦は、その象徴だ。しかし、これらは“やればできる”類の話ではない。半導体は、技術、人材、装置、材料、サプライチェーン、顧客基盤、地政学──あらゆる要素が高度に統合された産業であり、根拠のない楽観は、必ず失敗を招く。
過去の日本は、この産業の構造と変化の速度を読み違え、正しい政策判断を持続できなかった。結果として、世界の最前線から脱落した。この歴史を直視しなければ、同じ過ちを繰り返すだけである。TSMC熊本もRapidusも、成功する可能性は決してゼロではない。しかし、それを実現するには、これまでと比較にならないほど徹底した現実認識と、継続的な実行力が必要になる。それが欠ければ、国策はまた失敗する。
私は、半導体産業を内部から見続けてきた経験をもとに、事実だけを、冷静に、正確に、タイムリーに伝えることを自らの責務と考えている。表面だけを追っていては、本質には到達できない。企業戦略も国策も、成功と失敗を分けるのは、華やかな発表ではなく、現場が積み上げる現実である。この現実を理解することなしに、未来の議論を行うことはできない。
本メルマガでは、読者の判断に資するために、半導体産業の構造変化、各国の戦略、技術の進化、サプライチェーンの実相を、淡々と、しかし徹底的に分析していく。AI時代における産業競争は、もはや後追いでは成立しない。正しい情報と正しい認識だけが、未来の選択を可能にする。私はその一助となるべく、これからも筆を執っていく。
バックナンバーには、「なぜ私はエルピーダを1年で去ったのか?」、「なぜ日本半導体の復権を目的としたセリートに 失望したのか?」、「大学で半導体産業を研究しているときに本当は何があったのか?」、「大学を辞してベンチャーを立 ち上げようとしたとき何が起きたのか?」―などを湯之上隆の物語として収録している。筆者自身の個人的なエピソードをさらけ出すことで、“日本の半導体村”の実像に迫っていただくのが狙いだ。
半導体や電機産業に携わるビジネスを理解するための一助として、また技術開発の方向性を見出すための手助けとし て、本メルマガをご活用頂ければ、著者としてこれに優る喜びはない。
Vol.340(26/02/19)露光装置は嘘をつかない-ASMLが映す20年後の覇権― |
Vol.339(26/02/05)TSMC熊本はアリゾナの二の舞になるのか-TSMC海外ファブが突きつける半導体投資の残酷な現実― |
Vol.338(26/01/22)無敵に見えるTSMCの歪んだ姿-AI革命2年半後の現実― |
Vol.337(26/01/25)崩れた「最先端=Apple」神話-TSMCの3nmから見える「需要の質的変化」― |
Vol.336(25/12/25)Googleの検索から生成AIの推論へのシフト-あなたの“1回の質問”は世界をどれだけ動かすか― |
Vol.335(25/12/11)世界半導体キャパシティの「危険な偏在」-OECD最新データが映し出す地政学の真実― |
Vol.334(25/11/27)AIが世界のメモリを食い尽くす-HBM需要急増とDDR DRAM永続不足の衝撃― |
Vol.333(25/11/13)私の新車はいつ納車されるのか-蘭ネクスペリアの半導体不足によるクルマ産業の混乱― |
Vol.332(25/10/30)TSMCはAI文明の心臓となった-2020~2025年のウエハ投入量が示す構造転換― |
Vol.331(25/10/16)EUVは、どの半導体メーカーが、何台持っているのか-強力なTSMCと脆弱なRapidus― |
Vol.330(25/09/25)『NHKスペシャル 1兆円を託された男 ―ニッポン半導体 復活のシナリオ― 』 を検証する |
Vol.329(25/09/04)“Made in USA”のAIサーバー製造は不可能−高関税で脅しても、できないものはできない− |
Vol.328(25/08/21)前工程装置市場の動向(その2)−5番目の100億ドルクラブ候補はPVD装置− |
Vol.327(25/08/07)さらば、Intel−10年後にIntelという半導体メーカーは無いかも知れない− |
Vol.326(25/07/24)中国メーカーの台頭が目立つ前工程装置市場(その1)−微細加工装置に関する企業別シェア− |
Vol.325(25/07/10)本格的なGate-All-Around(GAA)時代の到来−先端Logic半導体メーカーの戦略と現在地− |
Vol.324(25/06/19)Samsungの半導体部門の変調—その2—−DRAMとNANDも不調− |
Vol.323(25/06/05)Samsungの半導体部門の変調—その1—−TSMCの背中が遠のくSamsung Foundry− |
Vol.322(25/05/22)トランプ関税による世界半導体産業への悪影響−3つのシナリオによる半導体市場の予測− |
Vol.321(25/05/08)論文数爆増! VLSIシンポジウム(その2)−その原因は中韓の大学の躍進− |
Vol.320(25/04/24)論文数爆増! VLSIシンポジウム(その1)−中国と韓国が怒涛の論文投稿− |
Vol.319(25/04/10)トランプ大統領は「ばか」なのか?−iPhoneのケーススタディ− |
Vol.318(25/03/27)米Intelの再建は可能か?-TSMCはIntelのFabを「運営」できるか?- |
Vol.317(25/03/13)2035年までの世界半導体市場予測-データセンター用の半導体が市場の半分を占める- |
Vol.316(25/02/27)開発とは何か? 量産とは何か? 歩留りとは何か?−2nmのLogic開発の難しさに迫る− |
Vol.315(25/02/13)「2mmの量産が難しい」ことを説明するのが難しい−やっぱりRapidus Impossible !− |
Vol.314(25/01/23)最高益でもどこか歪んだTSMCの業績-先端、米国向け、HPCに大きく依存- |
Vol.313(25/01/09)SK hynixがリードする広帯域メモリHBM-台風の目となるのは中国CXMTか?- |
Vol.312(24/12/26)AIサーバー頼みのファウンドリー−成熟プロセスの約半分は中国が握る− |
Vol.311(24/12/12)AIが牽引する世界半導体産業−その2−−ASMLのEUVが果たす役割− |
Vol.310(24/11/28)AIが牽引する世界半導体産業-その1--生成AIによるウエハ需要の変化- |
Vol.309(24/11/14)CoWoSのCapacityとテクノロジーの展望−CoWoS-Sに代わってCoWoS-Lが主役に− |
Vol.308(24/10/24)日本半導体への意見が「笑ってしまうほど正反対」になる理由−1次方程式「y=ax」の係数「a」が問題− |
Vol.307(24/10/10)日本半導体産業の最大の弱点は設計−熊本県菊陽町の観光− |
Vol.306(24/9/26)AIサーバー市場の分析−23-24年の“GPU祭り”は序章に過ぎない− |
Vol.305(24/9/12)台湾主催のフォーラムは“台湾”だった−TSMC熊本工場の疑似体験− |
Vol.304(24/8/29)3D NANDのHARCにおけるLamとTELの攻防−Samsungの570層に使われるのは、どっちだ− |
Vol.303(24/8/15)TSMCの日米独工場の展望−TSMC熊本工場の復習と続報− |
Vol.302(24/7/25)TSMCの業績は好調なのか?−どうも絶好調とは言えない− |
Vol.301(24/7/11)TSMC熊本の第1工場の実態−TSMC熊本工場は持続可能でない− |
Vol.300(24/6/27)半導体製造装置市場の分析(その2)−日本の前工程装置産業のシェア低下が止まらない− |
Vol.299(24/6/13)半導体製造装置市場の分析(その1)−2023年の不況時に露光装置市場が急成長− |
Vol.298(24/5/23)シャープが液晶パネル製造から撤退−半導体と液晶の技術者の互換性− |
Vol.297(24/5/9)論文数が激増したVLSIシンポジウム2024(その2)−今後VLSIシンポジウムにどう接していくか− |
Vol.296(24/4/25)論文数が激増したVLSIシンポジウム2024(その1)−VLSI2024の概要と投稿・採択論文数の動向− |
Vol.295(24/4/11)NVIDIAのGPUのもう1つのボトルネック、HBM−なぜHBMの出荷個数が劇的に増えないのか− |
Vol.294(24/3/28)なぜNVIDIAの株価が高騰するのか−その原因はTSMCのCoWoSのCapacity不足にある− |
Vol.293(24/3/14)半導体市況は2024年に本格回復しない?−問題はロジック半導体の出荷低迷− |
Vol.292(24/2/22)「日本の半導体政策は間違いだらけ」の3件の講演−「ニュートラル」な意見とは何か?− |
Vol.291(24/2/8)ファウンドリーの本格回復はいつか−TSMCの異変はいつ解消するのか− |
Vol.290(24/1/25)AI半導体とファウンドリーの展望−ファウンドリーの本格回復はいつか− |
Vol.289(24/1/11)最後のDRAMとNAND価格の分析−SK hynixの躍進とKIOXIAの凋落− |
Vol.288(23/12/28)中国SMICはブレイクするのか?−ASMLからArF液浸を爆買い− |
Vol.287(23/12/14)ここ最近解明できた3つの謎−Rapidus、High NA EUV、EUVペリクル− |
Vol.286(23/11/30)経営統合に失敗したキオクシアはどうなる? |
Vol.285(23/11/16)なぜJSRは産業革新投資機構の傘下に入るのか |
Vol.284(23/10/26)「2nmの量産が難しい」ことを説明するのは難しい−どうしたら分かってくれるんだ?— |
Vol.283(23/10/12)DRAM+NAND合計のメモリメーカー別売上高シェア-キオクシアとWDは統合しないと生き残れない?- |
Vol.282(23/09/28)NANDの企業別売上高と設備投資から見えてくるもの―キオクシア+WDマジック!― |
Vol.281(23/09/14)個人事業主の生き方―自分の本質は「焼き芋屋」である― |
Vol.280(23/08/24)DRAMとNAND価格の分析―メモリ市況の回復には時間がかかる― |
Vol.279(23/08/10)史上最悪レベルの半導体不況はいつ回復するのか |
Vol.278(23/07/27)次世代リソグラフィワークショップ(NGL)への参加 |
Vol.277(23/07/13)各種後工程製造装置の出荷額と企業別シェア |
Vol.276(23/06/22)各種半導体製造装置の企業別シェア(後編)―前工程装置の企業別シェア(2回目)― |
Vol.275(23/06/08)各種半導体製造装置の企業別シェア(前編)―100億ドルを超える市場規模の製造装置― |
Vol.274(23/05/25)VLSIシンポジウムの記者会見(後編)―TechnologyとCircuitsのハイライト発表― |
Vol.273(23/05/11)VLSIシンポジウムの記者会見(中編)―投稿・採択論文数の分析:世界で最もアクティビティの高い機関は?― |
Vol.272(23/04/27)VLSIシンポジウムの記者会見(前編)―概要とタイムテーブル― |
Vol.271(23/04/13)文春新書 『半導体有事』 執筆奮戦記-- |
Vol.270(23/03/23)日本政府がフッ化水素ビジネスを破壊した-日韓政府が関係修復しても手遅れ- |
Vol.269(23/02/09)半導体史上最悪の半導体大不況の到来―Intelとメモリメーカーは持ちこたえられるか?― |
Vol.268(23/02/23)今回の大不況はリーマン・ショックを超えか?(後編)-DRAM、NAND、MPUは過去最悪の落ち込み- |
Vol.267(23/02/09)今回の大不況はリーマン・ショックを超えか?(前編)-1年前の「メモリ不況は当分来ない」は大外れ- |
Vol.266(23/01/26)2022年の世界半導体売上高ランキングで1位になったTSMC-その前にあまりに支離滅裂な「NHKスペシャル」- |
Vol.265(23/01/12)なぜTSMCが米日独でファウンドリを建設するのか-厳しすぎる米国の対中規制が台湾有事を誘発する?- |
過去のバックナンバーのタイトルまとめPDFファイルのダウンロード
こちらからは、過去のバックナンバーのタイトルをまとめたPDFファイルをダウンロードすることができます。
湯之上隆
1961年生まれ。静岡県出身。1987年に京都大学大学院(原子核工学専攻)を修了後、日立製作所入社。以後16年に渡り、中央研究所、半導体事業部、エルピーダメモリ(出向)、半導体先端テクノロジーズ(出向)にて、半導体の微細加工技術の開発に従事。2000年に京都大学より工学博士取得。
現在、微細加工研究所の所長として、半導体や電機産業のコンサルタント及びジャーナリストに従事してる。著書に『日本「半導体」敗戦』(光文社)、『「電機・半導体」大崩壊の教訓』(日本文芸社)、『日本型モノづくりの敗北 零戦・半導体・テレビ』(文春新書)。
湯之上隆のウェブサイト:http://yunogami.net/