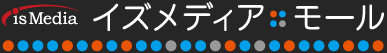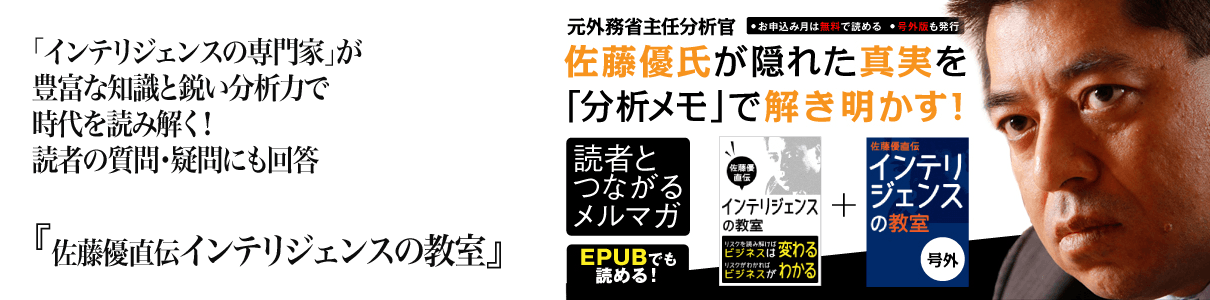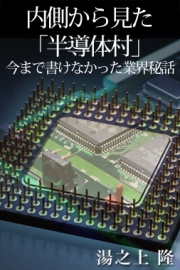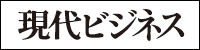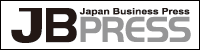イズメディア・モールへようこそ!
コンテンツ自慢のメディア集団 isMedia(イズメディア)のショッピング・モールです。日本を元気にするコンテンツやアイテムを販売してまいります。第一弾はコンテンツ。現代ビジネス、JBpressなど、イズメディア・ネットワーク参加媒体が選りすぐった執筆者のとっておきの情報を、いろいろなカタチで読者の皆様にお届けします。有料メルマガや電子書籍はもちろんのこと、それらデジタル・コンテンツとセミナーなどリアルなイベントを組み合わせた新しい試みにも挑戦していきます。
ニュース
-
2025/03/12【重要】システムメンテナンスのお知らせ(2025年3月28日〜3月31日)
-
2023/09/25適格請求書等保存方式(インボイス制度)についてのご案内
-
2021/11/01クレジットカード会社の決済ルール変更に伴う、カード情報の登録・更新のお願い
申込月発行号の無料キャンペーン実施中!
メルマガのお申込み月の発行号が無料になります。ぜひメルマガの内容をお確かめください。
※お申込みの際にクレジットカードのご登録が必要となることを予めご了承ください。
メルマガのバックナンバーを購入できます
ご購読中のメルマガのバックナンバーを購入できます。詳細は「バックナンバーなど」をご参照ください。
イズメディア・モールとは
コンテンツ自慢のメディア集団 isMedia(イズメディア)のショッピング・モールです。
日本を元気にするコンテンツやアイテムを販売してまいります。
第一弾はコンテンツ。現代ビジネス、JBpressなど、イズメディア・ネットワーク参加媒体が選りすぐった執筆者のとっておきの情報を、いろいろなカタチで読者の皆様にお届けします。有料メルマガや電子書籍はもちろんのこと、それらデジタル・コンテンツとセミナーなどリアルなイベントを組み合わせた新しい試みにも挑戦していきます。